
こちらの色打掛のイメージは、一瞬で決まりました。
我が家には「風彩染」という独特の染め技法があります。その中に「清華ーせいかー」という技法があります。
それを使えば、また、世界に一枚、独特の色打掛が出来ると考えました。
この衣装、実は師匠に染めてもらおうと思っていました
実は、製作を考えたのは2年ほど前。しかし、日々の着物づくりに追われ、師匠を急かすことも出来ません。
ここは、自分でやろうと思い立ち、2年前に預けた生地を開けてみると。。
少し師匠の頭を覗く。色見本が一部に付いていました。
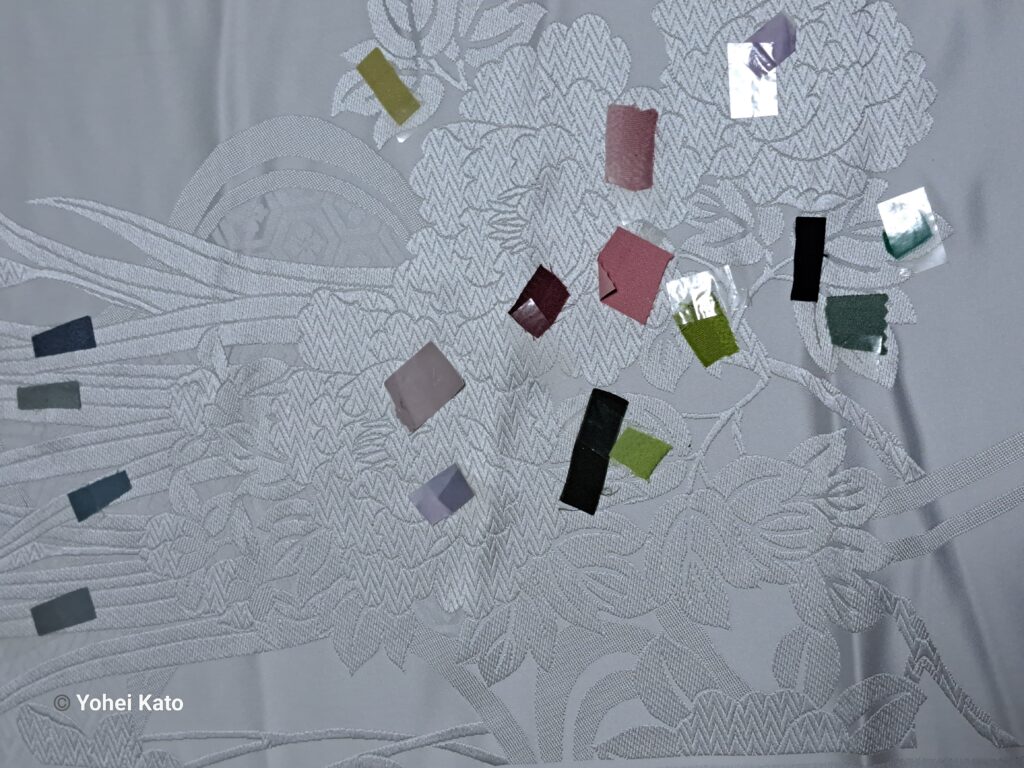
本人も忘れていたのですが、途中まで考えていてくれたのですね。
めったにない機会、師匠の色遣いのことが見えてきます。
そんなことをするのは10年ぶりくらい。
しかし、濃度などはここから実験していきます。
「ときつかぜ」の染め方は、「生地を濡らしながら染めていく」技法です。
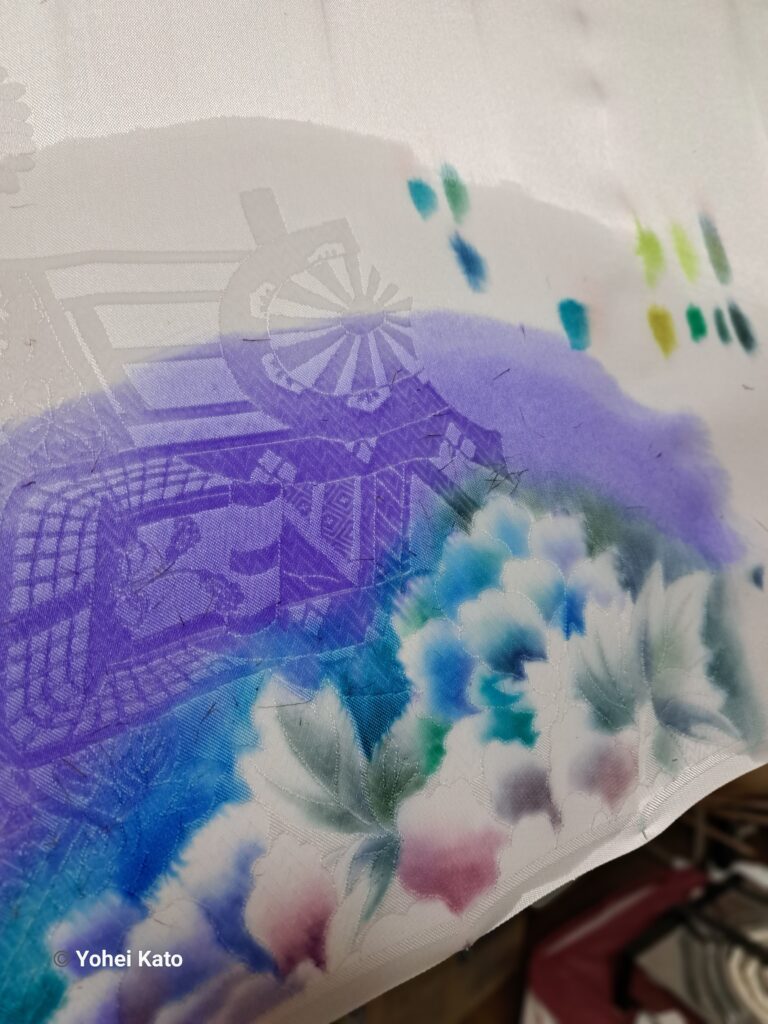
生地の分厚さによってや、乾き方で、濃さが凄く変わってしまいます。
濡れてるときは、色が濃く見えるからです。
そして、この染は、ほんの少しの濃さの違いで、全く仕上がりが変わります。
「イメージと違ったけど、これも良いか」ということが許されません!!
師匠が勧めたやり方と、自分のイメージが違った
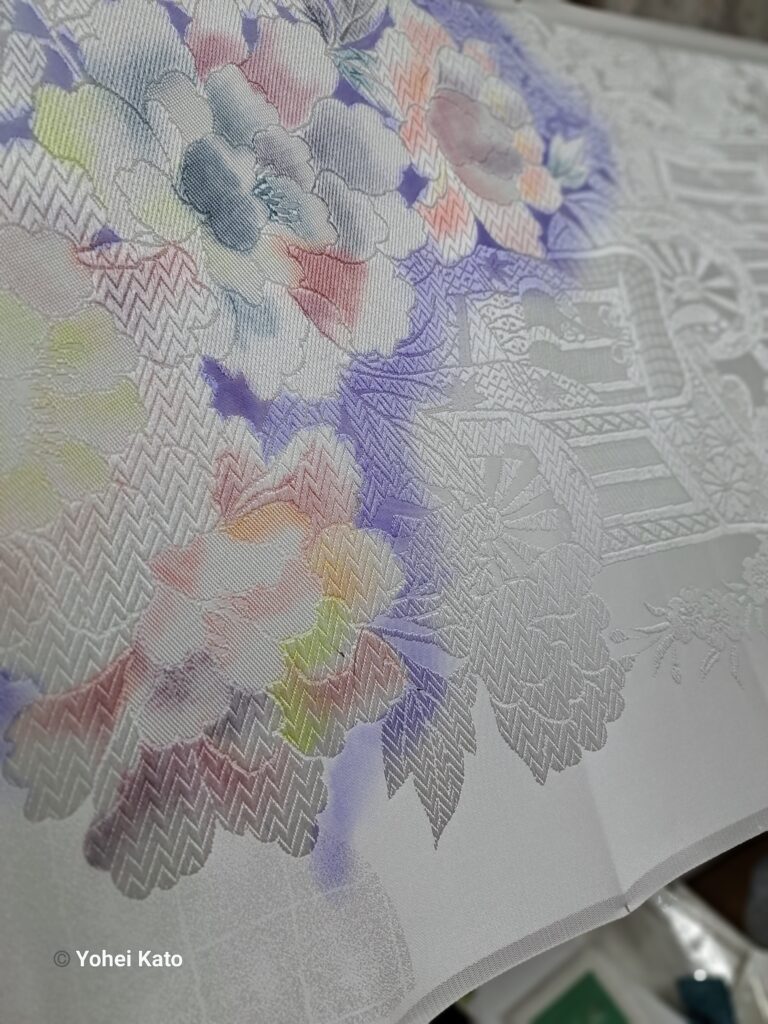
師匠が作ってくれた色は、師匠が今回勧めてくれたやり方に合わせた考え方。
そこの差も埋めなくてはなりません。実験は続きます。
そして、片袖を染めてみました。

片袖を染めている間、途中で作業をやめることは出来ません。
その時間は13時間。
13時間の全集中です。
13時間同じペースで染め続けるのです。なぜなら、濡らしながらなので、途中休憩しようものなら、どんどん乾いていくので。
そして、この片袖を持って、師匠のところへアドバイスをもらいに行きました。
今回は慎重です。師匠が作った染めに、敬意を払ってです。ではまた②でお会いいたしましょう☆


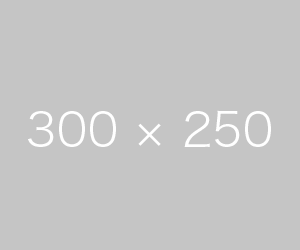
コメント